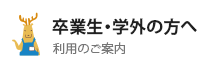また会う日まで(上・下)
尾崎紀世彦の歌?否、圧倒的ボリューム感で迫る小説界のヴァーリ・トゥード。
ジョン・アーヴィング作品史上最長の新作。見た目はいつもくらいの厚みの2分冊だが、ページを繰ってみると紙が辞書くらい薄くて驚く。それだけテキスト量があるということ。繰っても繰ってもなかなか残ページが減らない贅沢さ(鬱陶しさ?)。翻訳が待ちきれないので原書を講読する作家の一人だけれども、初めて目にするような英単語も散見されるので意外と読みにくい。悲しいかな僕の覚束ない英語力では大筋は追えても細かな描写やニュアンスまでは十分把握できないので、日本語版が出たら改めて読むようにしている。ところが、翻訳というものはなかなか厄介なもので訳者のクセが出る。どの作品とは言えないがあまりに読むのが苦痛で途中で放り出したこともある(文章のリズムが僕に合わないという個人的な事情であってその方の翻訳者としての力量を問うものではない)。裏方作業の翻訳業とはいえ近頃はすっかり有名人になってしまった東大の柴田元幸先生さんみたいな方がたくさんいれば、アメリカ現代小説ファンにはありがたいのだが。
さてこの作品。作者が自賛するように最高傑作とは思えないが、よくも毎回こんなファニーなプロットと登場人物を思いつくなと尊敬してしまう。ポコポコと人が死に、いたるところにセックスが溢れた話なのに、決して湿っぽくならないのが不思議でならない。人間の日常と非日常との交錯を極端にディフォルメし、悲痛な出来事を滑稽な描写に昇華するこの作家の力技が、哀切な読後感を深くそして長く継続させる。
幼子の頃より年上の女性を魅了してきたプレイボーイの主人公ジャック・バーンズはクィーアなB級映画ばかりに出演するハリウッド男優。父親の顔を知らない彼がタトゥーアーティストの母親に手を引かれながら、二人を置いて逃げた父ウィリアムを追って北海沿岸のヨーロッパ諸国を旅する幼少時代のエピソードから物語は始まる。オルガンの名品を訪ねて教会を巡り放浪する父親。手がかりはウィリアムの全身にくまなく施された楽譜の刺青と彼に捨てられた女たち。母アリスは同業者のコネクションを頼って各地で刺青を入れて回る夫の足跡を辿るも徒労に終わり、カナダで息子を女学校に入学させる。女だらけの環境の中でハンサムな父親に似たジャックは必然的に周りの人々を幻惑することとなり、演劇とレスリングを学びながら成(性)長していく。彼はやがて映画俳優になり成功を収めるものの、尋常ならざる環境に育ったことに起因する心の病から精神病院に通う日々が続く。あるとき母親の死をきっかけにして父親を探す旅に出る。そして次第に明らかにされる意外な真実・・・・。
梗概をまとめるのが難しいくらいストーリーが突拍子もなく、めくるめく変調を繰り返していく。そんな小説の醍醐味を存分に堪能できる一冊だ。