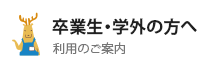J.S.バッハ「ブランデンブルク協奏曲第5番 BWV1049」
青春時代に、一曲の音楽を聴いて涙した経験を持つことが、その人の人生を変えてしまうかも知れない、 ということについて。
バッハが好きである。
「好きである」というと友達感覚のようであまりに恐れ多いが、自分にとってバッハは離れられない永遠のテーマである。
わたしが初めてバッハを意識したのは高校1年生の音楽の時間。
音楽室で流れてきた曲が「ブランデンブルク協奏曲第5番第2楽章」。
初めて耳にする旋律。適当な表現が見つからないが、腰の方から脊椎を氷が這い上がって行くような感動(みなさん、そんな経験ないですか?)をその時覚えた。
普通、音楽に感動するとき「美しい」という表現が使われる場合が多いが、 バッハの旋律は美しさを超えて、「人生」を語っていた(ように思った)。
だれにでも青春時代はある。こんなわたしにもあった。
その真っ只中にあった高校1年生。
他人を通して自分を意識し、自分の存在の小ささ、不確かさに不安を感じ始めるとき。気分が揺れ動きやすい頃。
その不安定な心に、「ブランデンブルク協奏曲第5番第2楽章」のもの悲しい旋律は、なんの飾りも誇張も衒いなく、しみ込んできた。
バッハの楽譜をみると譜面の意外な単純さに驚く。
しかし、いざ弾いてみるとバッハは難解である。
感情移入をすると、たちまち何を演奏しているかわからなくなってしまう。
バッハは宗教音楽家であり、自分の人生を音楽という形で神に捧げた人。
神の存在は普遍的であり、個性的であってはならないということだろうか?
バッハは深い。
いずれにしろ、生れた時には既にバッハの曲が存在していたことを、神に感謝したい。
(text:bach憧憬)