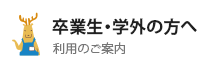『胡同の理髪師』
北京の下町・胡同(フートン)で生きる93歳の老理髪師―彼の日常をドキュメンタリータッチで描いたヒューマンドラマ。
主役のチンお爺さんは93歳、実際に胡同で生活する理髪師だ。もちろんこれが映画デビュー、世界最高齢の新人俳優となる。主演だけでなく、他の出演者もほとんどが胡同で暮らす人々で、彼らの織り成す日常が心温まる一本の作品となっている。
パンを用いず、固定されたカメラで捉えられていく市井の人々。小津安二郎を彷彿とさせるが、小津とは違って少し上のアングルから撮られていることが多い。ちょうど小柄なチンお爺さんの傍らに自分が立って話を聞いているような位置だ。シーンによってアングルは変わるが、常にチンさんの側に付かず離れず見守るような視線になるので、まるで自分もそこにいるような、胡同の一員となったような気分になる。
素人の老人を主人公にドキュメンタリータッチで描くということで、むかし観た『森の中の淑女たち』というカナダ映画を思い出した。この作品も主役は素人のお婆さんたち。脚本らしい脚本もなく、彼女たちの実体験を元にストーリーが展開していく。そういった点では似ているのだが、その結論はまったく正反対へと進んでいく。『胡同の理髪師』に登場するお爺さんたちは、いかにして死ぬかを考えているが、『森の中の淑女たち』のお婆さんたちは、いかにして生きるかを考えている。これは国や文化の違い、胡同という生活の場と森という非日常の場との差異によるものかもしれないが、やはり男と女という性別の違いなのだろうか。
自分の祖父もそうであった。二年前、チンお爺さんより10歳若い83歳で逝ってしまったが、常に死について考えていたように思う。毎年正月には決まった場所で写真撮影をし、自分の入る墓を準備、財産の整理までしていた。そういったことを考えると、若者にとっての将来は就職や結婚などであるように、老人にとっては死こそが将来なのだと実感させられる。しかし、それは悲しいことのようで実はごく当たり前のこと。自らがその場に居合わせているとそんなことに思いを馳せる余裕すらないが、第三者の立場で遠く離れた場所から眺めてみるとよくわかる。入院中も退院したら何がしたいとか、どこへ行きたいとか言う代わりに、わしが死んだらあの金をこうして、家をどうしろとか、そんな話ばかりをしていた。何十年も愛用した剃刀と刷毛でしか髭を剃らず、歩ける状態ではないのに自分でトイレに行きたがったりと、介護する側からは面倒なことも多かったが、今になってやっと、あの頃の祖父の気持ちが理解できたような気がする。
そんな実体験と重なったせいか、観ているうちに涙が止まらなくなった。いや、そんな経験をしていなくても老人たちの清廉な姿は涙を誘うだろう。それは決して悲しい涙ではなく、自然と溢れてくる温かい涙だ。きっと、こういうのを本当の感動というのだと思う。
『胡同の理髪師』 監督:ハスチョロー
第七芸術劇場公開中、3/29より京都シネマでも公開