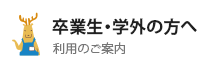詩人と女たち
どう考えてもサイテーの爺ィちゃうんケ(無理して京都弁)。
マット・ディロンがチャールズ・ブコウスキーを演じる『酔いどれ詩人になるまえに』がDVDでリリースされました。懐かしいミッキー・ロークの『バーフライ』と観較べてみたいところ。
何不自由なく凡庸な学生時代を過ごしてきた当時二十歳そこそこのウブな文学青年(僕のこと)にとって、パンキッシュで薄汚れた実生活を自身の小説に投影するブコウスキー作品に出会い一発で痺れました。一時期は郵便局員という謹直なお勤めをしていたのだから決して無頼というわけではないのですが、酒と女性に耽溺する私生活をありていに暴露するその潔さにわが身には不相応ながらも憧れたものです。フォークシンガーの中川五郎さんが孤軍奮闘、翻訳と紹介をされていたこともこの作家の印象を強める一因でした。
しかし不思議なもので、年齢を重ねるにつれてデカダンな生き様に心酔していた過去のファンタジックな自分を思い返しては恥ずかしくなることがあります。そうでなくとも、かつてはマイナーであった作家が、ベッソンの製作で映画化(『つめたく冷えた月』)されたり、新刊単行本(『町でいちばんの美女』)の帯にたけしが賛辞を寄せたりして脚光を浴びはじめた頃から次第に僕のブコウスキー熱は冷めていきました(なぜ世間から注目されるとスポイルされたような気分になるんでしょうね)。
ブームから十数年が経ち、映画をきっかけに再び若い世代に読まれるようになるのでしょうか。毒にも薬にもならないような純愛小説の対極に位置するブコウスキーのスカムノベルは衛生的な無菌状態を好むであろう若者たちにどのように受け入れられるのか興味深いところではあります。
(text:情是)