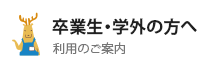ぼくの小さな恋人たち
いきなり「美醜私論」から入る。
やはり見た目のいい人はトクである。ていうかブッちゃけていえば見た目が総てである。ナルシスティックな心の安寧を経てはじめて身辺の事象が動き出す。コンプレックスだらけの人生に建設的な進展はありえない。平凡なルックスの人でもスバ抜けた特技とか知性があれば容貌の欠陥を補償しうるが、それすらもない人(僕を含めて)はどうしたら自信を持って生きていけるのだろう。美男美女であればオプション(才能や性格)がどうであれなんとかテキトーに人生を切り抜けていけるような気がするのだが。真に疎外されたプレカリアートの定義とは「ブサイクで才能もないフリーター」と端的に括れるのではないだろうか。こんなこと書くと怒る人がいるので、あくまで自虐ネタ(現在はフリーターではないけど)であるということを断っておきたい。そう考えると世間に臆することなく堂々と美人論なんて発表してしまう井上章一先生ってスゴイなと思う次第。
なんだか偏屈なコメントにはじまったが、いったいおまえはナニが言いたいんやといえば、「外人さんはトックやなぁー」ということなのである。いや、この手の映画は決して日本人の役者を使ってできるもんじゃない。お人形さんのように美しい外人さんたちがスクリーンで動き回るからこそ、こんな素敵な映画ができるのである。そしてこの映画はあのトリュフォーの『大人は判ってくれない』さえも霞んでしまうくらいの存在感で、ボクの心の中に巣食ってしまっている。
内容はといえば、ユスターシュ監督の少年時代を再現したお話で、映画的にはありふれているかもしれない。学校生活、悪友たちとのよしなしごと、家庭内の不協和音、年長の少年たちに混じって覚えていく背伸びしたお遊び・・・。どこにでもありそうな挿話群でありながら、この映画を他の回想録と隔てる特長は、詩情豊かな映像とリズムである。少年少女たちだけでなく、田園風景の細部に至るまですべてがキラキラと輝いて見える。カメラは完全にその存在を消し去り、どこまでも透明感を湛え、観客と映画との距離をなくしている。もちろん前述のようにマルタン・ローブ少年を含む若く美しい役者たちの功績も忘れてはならない。
女の子の小さな胸のふくらみに手を触れたときに湧き起こる男としてのセクシュアリティの淡い目覚め。好きという感情の対象が同性でもあり異性でもあり大人でもあり動物でもあるようなまだ未分化の混沌とした状態の中から、密度と比重を伴いながら次第に差異として明瞭に実感しはじめる年頃。そんな『小さな恋のメロディ』や『マイライフ・アズ・ア・ドッグ』的な思春期前の甘酸っぱく気恥ずかしいイノセンスな時期より一歩だけ踏み込んだ(成熟した)微妙なラインを描いていて秀逸である。何度でも観たくなる。