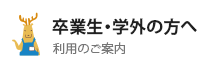エデンへの道
気の弱い人はくれぐれも鑑賞しないように。ブラッケージの『自分自身の眼で見る行為』とよく似た触感のドキュメンタリー映画です。
淡々と死体解剖作業を映したとても正視できないグロいシーンが満載(血とか臓物とかにめっぽう弱い僕は何度も眩暈におそわれ嘔吐をもよおした)。ぬらぬらとした臓器の質感やギトギトぎゅにょっとした黄色い皮下脂肪、うにょうにょしたクリーム色の脳みそなどが網膜を通して僕のか弱い心臓を苛烈に刺激し、不整脈がよりデタラメなリズムを刻んだ(はぁっはぁっ・・・)。
このように書くと死体解剖の衝撃性だけを弄んだいい加減なドキュメンタリーのように聞こえるが、映画構成の質は高い。主人公となる死体解剖医の日常や独白などを要所で挿入することにより、生と死の対照性が際立ち、観客を死体解剖の熱狂からクールダウンさせることで、テーマに対する思索の距離感を維持させている。
flesh【肉】。死んでしまえばただの肉塊。そこには死の尊厳や精神の残骸など全く認められない。解剖室に並べられた痩せさらばえた死体、ぶくぶくと醜悪な肉塊を、解剖医たちはメスや電動ノコギリを使って、実にあざやかな手並みで切り分けていく。極めて事務的にそして機能的に。その無駄のない手際が、彼らが「死」に携わるプロフェッショナルであることを物語る。延々と続く解剖シーンはわれわれに死というディスコミュニケーションについて再考することを強いながら、一方ではその鮮烈なインパクトによって何らの思考の介在も拒んでいる。
人は、死者の生前のイメージや肉体に執着するものだ。しかしそんな甘い感傷もこのフィルムによって粉砕される「人間なんてモノにすぎない」という認識を否応なしに刻み込まれる。
脳生理学が主張するように、人間の知・情・意という精神活動がすべて脳からの働きによるものならば、劇中こっぽりと脳を抜き取られた後のあの頭蓋の空虚は、まさに人生の空虚そのものではないか。なんと唯脳論というのは、かくも悲しく切ないものなのか。しかし決して虚無的になってはいけない。「この映画を観て、人間にとって大切なのは肉体ではなくて心なのだと実感させられました」みたいな優等生的な逃げ口上もわからないではないが、現世においては、肉体=生こそ至高なのであり、同時に消耗品なのだ。「人間は肉塊だ」という即物的な諦観を乗り越えたうえでこそ、いまここに「在る」ことの素晴らしさを再認識し、刹那を悔いなく生きていく真摯な心構えができる。たとえその認識そのものすらが脳に依拠するものだとしても。
映画と併せて、根本敬著『人生解毒波止場』(洋泉社)収録の死体解剖見学記を読んでみてください。こちらは面白いエピソード満載で、ボクの辛気臭いシリアスな文章を笑い飛ばしてくれるような爽快なコラムです。脳についてもっと詳しく知りたい方には大木幸介教授の諸著作(新書版もたくさん出版されているので)をおすすめします。