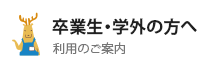『においの歴史:嗅覚と社会的想像力』(アラン・コルバン[著])
いま外を歩いていて、「におい」を感じとることのできる人は果たして
何人いるだろうか?
せいぜい車の排気ガスのにおいがする、といったところであろう。
いま何かのにおいを感じとることは、とても難しい時代となっている。
昭和のことがノスタルジックに語られることが多い昨今であるが、
それは多分に、無くなってしまって、いまは目にしたり触れたりする
ことができなくなったものに対して郷愁の思いを抱くせいだろう。
そんな「なくなってしまったもの」たちの中に、「におい」も含まれるのでは
ないか?とわたしは考えている。
昭和30年代~40年代頃の日本には、いまよりはるかに多くの種類の
においがしていたと思う。
田畑の肥料のにおい、商店街の焼き魚や野菜のにおい、木の葉や草の
発するにおい、本や雑誌のにおい、レコードのにおい、レンゲや菜の花の
におい、土のにおい、駄菓子屋のにおい、病院の消毒液のにおい、などなど。
「におい」は言うまでもなく「嗅覚」のはたらきによるものであり、他の感覚器官と
同様に、記憶と深く結びつくものである。したがって、土や草花のにおいをかぐことで、
遠い子どものころの記憶が甦ってくることは、よく経験するところである。
ひとは記憶や経験の積み重ねを大切にしながら成長をしていく存在だと思う。
そう考えると、「におい」すなわち「嗅覚」が磨かれる機会もなく成長していく、
ということは人間にとって大切ななにかを喪失してしまっているのではないか、
と思えてならないのである。
『においの歴史 : 嗅覚と社会的想像力』
アラン・コルバン[著] ; 山田登世子,鹿島茂訳
情報館所蔵:3F閲覧室 204∥C88
(text:bach憧憬)