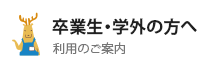高学歴ワーキングプア
「フリーター生産工場」としての大学院、という悲痛な副題からも伺えるアカデミズムの闇。・・・というか雇用格差の一端。
大学院を出てみたところで常勤の大学教員になれる道は限りなく狭く、ただ不条理な暗澹たる世界が待ち構えていますよ、という自叙的な哀話。著者の水月昭道さんは、現在、京都の某大学に非常勤教員としてお勤めされている身分の不安定な若手学者のおひとり。専任教員になりたくてもなれず、かといって民間企業に職を求めても高学歴者に対する了見の狭さや年齢的な問題で転職もままならず、非常勤講師を勤めながらアルバイトに身をやつすといった同僚たちのやるせない経験が赤裸々に語られる。ルサンチマンに駆られることなく若手院卒生たちを取り巻く現状を淡々と紹介するその佇まいには好感が持てる。これから大学院への進学を検討している学生さんは、まずは本書を読んでから慎重に再考してほしい。
以前、筒井康隆さんの『文学部唯野教授』という小説を読んで大爆笑したことが思い起こされる。一般常識から逸したアカデミズムの屈折した人間関係を滑稽に描いた作品であるが、まんざら虚構の話でもなさそうだということも聞く。専任教員になるのも難しければ、なったらなったで講師→助教授(今は准教授)→教授という昇格も難しい、たいへんイヤな苦労の多い世界のようである。
研究面での教員の業績は発表した論文の数で測られる。優秀な有期雇用の教員にとってなにが不条理に感じるのかというと、大学業界の雇用市場の狭さというよりも、研究業績が現在の立場や待遇に反映しないというアンフェアな状況に対してである。自分たちが非常勤のコマをいくつかの大学でかけ持ちしても年収200万円にも満たない苦しい生活の中で、研究資料費や学会に出席する交通費などの諸経費を自腹で購いながら、ピアレビューを通過した学術論文を何本も発表し続ける一方で、個人研究費などの公費もあり所得面でも恵まれていながら学会はおろか学内紀要にすら一本も投稿しない専任教員がいるという、成果主義の通用しないアカデミズムの世界の現実に歯噛みしているのだ。もちろん論文を発表しなくとも(あるいは専門が細分化しすぎているため単に人知れず発表しているだけかもしれないが)、教育に情熱を注いでいる教員もたくさんいるだろうし、役職の肩書きなどがついてしまった日には煩瑣な事務に追われて研究どころではなくなる。年中、多数の教員を学内行事にかり出す大学もある。ただ事情はともかくも、いったん専任教員にさえなってしまえば一般的に人事考課はなく、テニュアという終身雇用が保証された身分であるがゆえに、研究者としての誇りを持って己にドライブをかけ続けておかないと、自分に甘くなって論文を書かなくなる可能性があることは事実だ。
研究活動の活性度において比較優位にある若い研究者が常勤教員になれないという世代間の不平等をなんとかできないものだろうか。現職の専任教員は論文など書かなくてもいいからせめても後続する若い世代の研究者たちのために、ひいては学生が優れた教員のもとで学ぶ機会を増やすために、もう少し能動的に彼らの身の上を考えてあげてもいいのではないかと嘆息する。たとえば、「優秀な非常勤教員をもっと専任登用するために、みんなで痛みをシェア(構成員の給与を一律削減)しましょう!」なんて救済の声を上げてくれると嬉しいのだが。
しかし、もし本当にそのような減給が現実となりそうになった場合、ワーキングプアなどの労働問題を専攻している常勤教員でさえどのように反応されるのだろうか。自らの既得権益に抵触してもなお、研究対象にエンパシーを感じるスタンスを堅持できるのだろうか。これは別に教員に限ったことではなく、大学職員やその他民間のサラリーマンにだって同じことがいえる。マンガ喫茶を寝床にしたフリーターのニュース映像を観て「可哀想に」と憐れむ人のどれほどに、仮に所属組織が待遇面で公平なワークシェアを導入したときに、所得水準の低下を甘受し諸手を挙げて利他的な変化を歓迎できる度量があるのだろうか。雇用格差を軽減する鍵は「同質労働に対する同一時給単価を前提としたワークシェア」にあると思っているが、現実レベルに落とし込むには正職員が共存の発想から給与カットという苦しみを受け入れる必要がある。2人でやっている仕事量を3人で負担できるなら、そして正職員として安定的雇用が確保される人が1人増えるなら、個人的には自分の所得が単純計算で2/3になっても構わないと思っている。
いうまでもなく大学とは非営利組織である。教育や研究、学生との交流が好きで大学に集っているはずなのにカネに妄執するような教職員は大学を去って民間企業に転職するか起業でもしたらいい。教員一人当たりの学生数を減少させて教育の質を向上させるには専任教員の増員しかない(あるいは教員数据え置きで入学者数の減少を待つのも同じ効果だが、ネガティブな処方なのでここでは除外)。それは現職教員にとっても教育にかかる負担の軽減や研究に充当する時間の増加も意味する。給与が減ったとしても悪い話ではないだろう。教員・職員の別を問わず、教育という仕事は学生と対面で密に係わるのが重要であり、それに従事する人間こそが財産であるはずだから、志のある教職員が1人でも多く在籍しているにこしたことはない。多すぎて困るということは絶対にない。
授業料が大半を占める大学の帰属収入のうち人件費支出を70%以内(50%以内という人もいる)に抑えることが大学経営を健全に保つ対策のひとつと言われている。だからといって「新たに常勤教職員を採用すべきではない」とか「雇用調整のきく非常勤の教職員で組織を補完すべき」という短絡的な発想に流れてしまう世間一般の大学経営者の考え方は明らかにおかしいのではないか。人件費支出率を一定基準内に収めたいなら、くどいようだが現職教職員の減給という既得権益に切り込めば済む話ではなかろうか。たとえやろうとしたところでおそらく労組やその他人間関係のしがらみもあって難しいだろうと想像できるが、非人道的な人事政策しか考えない経営者や既得権益を死守しようとする正規教職員がこともあろうに人を育てる「教育」に従事しているのだとしたらなんともシニカルな話ではないか。
18歳人口が減り続けるなかで各大学は財源確保のために入学志願者募集に奔走しているが、節操なく滑稽な名前の学部を新設してアイキャッチを目論むのではなく、地に足を着けて組織を存続させるためにも大幅減給&ワークシェアは妙案だと思うのだが。試算したことがないのであまりいい加減なことはいえないがいつかシミュレーションしてみたい(もしかしたら授業料の抑制さえも検討できるかもしれない)。僕に限らずバブル崩壊を若い時分に経験した人間の多くは「カネはあったらいいな」という程度であまり頓着せず高収入には拘泥しないようだから、将来的には実現可能ではないかと考えている。もしそのようなチャンスが到来したときに人事制度改革が頓挫するのだとしたらその要因はおそらく老害によるものだろう。カネは誰だってほしいが、これからの時代に必要なのは「ヤセ我慢の美学」と「共生の思想」である。
は〜、疲れた・・・。情の薄い今の世の中では現実味も薄そうな夢想はもう止めて、優秀な院卒者に対してはささやかながらも即効性のありそうなソリューションを以下に提案してみたい。
なぜ修士号・博士号取得者は大学専任教員の道を探るのか。彼らは大学職員を目指せばいいのではないかと思う。職員なら応募要件として専門性がさほど問われることもなく、ジェネラリストとして採用される傾向にある。昨今の募集状況をみていても教員よりはまだ門戸が開かれているように見受けられる。研究者マインドをもった人間なら、とりわけ教務課や図書館などの教学支援部門で必ずや能力を発揮するにちがいない。「学生に論文作成を指導できる職員」「教員サイドの気持ちを一研究者として汲み取れる職員」「非常勤教員として教鞭を執る職員」といった職務特性融合型職員が大学にもっと増えたら素晴らしい組織になるのだろうに、ね。